遭難捜索・登山届け 愛宕山 ― 2016/06/18

写真:遭難者捜索で右京警察の方への報告と情報交換
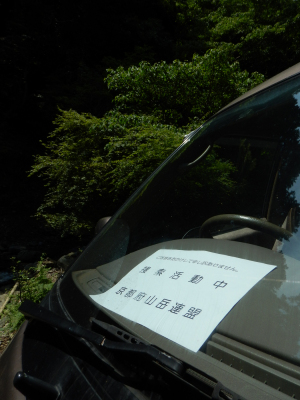
写真:京都府山岳連盟で捜索協力

写真:沢装束を入れたザックと、清滝までの足のTREK7.9FXたぶん2007年モデル
今日は、MTBで朝早くから走る予定にしていたのですが、前夜に所属山岳会より、遭難者捜索の要請があり、参加しました。
遭難者は68歳の男性で、4日前に愛宕山に登り、下山していないとのこと。愛宕山というのは、シビアな山ではないのですが。
警察や消防も捜索したけれど、京都府山岳連盟に協力の要請があり、私の所属している山岳会も岳連加盟のため、情報が届いた次第。
登山道他はくまなく捜索したけれど、発見できず、岳連には、沢筋中心に捜索して欲しいとのこと。
所属山岳会からのメールも、沢装備で懸垂下降ができる人、というオーダー。
私も会に入ってからそのへんのことを学ばせていただいたので、参加した次第。
朝、6時半に愛宕山の登山基地である清滝というところが集合場所。家を6時に出てコンビニで行動食等を買い、6時10分発で、遅刻しそうで申し訳ないと思ったけれど、シティコミュータークロスバイク・リアキャリア付き、に登山ザックをくくりつけて、無理なく走ったら、清滝にはパンクチュアルに着き、ウチから清滝は、たった20分か、私が毎日通勤している大阪・梅田から会社までの歩きの時間よりも近い、と右京区民にとって愛宕がいかに近いのか、改めて認識した次第。
で、集合地点には岳連加盟山岳会の方々が集合されており、担当を決めてそれぞれのエリアを捜索。亀岡の山岳会等の方々は、別の地点を出発して捜索。
沢筋中心に捜索したのですが、見つからず、愛宕神社のところでは右京警察の方4名と出会い、状況を報告。
下山も登山道外のところを含めて捜索しました。下山したところで消防の方と出会いました。消防の方は、これまでかなり大規模で捜索されて、滑落しそうなところとか登山道はくまなく捜索したけれども、見つからないとのこと。
通常、警察や消防は、「ここに遭難者がいる」ということが明かな場合、解決に向けた体制を組みますが、登山届けがなく、「どこに登ったのかよくわからないんですけど、帰ってこないんです」という登山行方不明者には、捜索範囲が特定できないため、対応が限られてしまうようです。
警察や消防を大規模に動員するということは、その分、別の場所での対応には負担になるわけで、公共の安寧に携わる立場としては、特定の案件だけに関わるわけにはいかないのは、市民感覚・納税者感覚としても仕方ないところでしょう。
ですから、登山届けというのは重要な意味を持つと、改めて認識しました。登山届け無しで行方不明になった人には、対処方法がどうしても限定されますが、きちんと登山届けがしかるべきところに出されていれば、当局としても、対応の仕方が判りやすい、ということでしょう。
今回の場合の愛宕山というのは京都近辺の人にとって火伏せの神様として親しまれており、山頂付近に愛宕神社があることもあって、愛宕さんに登るのに、いちいち登山届けを出す、という習慣はありません。「登山」ではなく「神社への参拝」なのに登山届けがいるんかい、という人がいるかもしれませんし。
では、なんで、警察や消防がすごい体制で臨んだかというと、遭難者のバイクが登山口にあったため。
それで、遭難者は確実にここから登って、ここに降りようとしていたという推論が成り立ち、警察消防は行動範囲が推測できるため、体制を組んだ、ということらしいです。
でも、これだけ探しても見つからない。神隠しにあったのか、そんな気持ちで解散しました。
その後、地元の人と話す機会があり、おばあちゃんですけど、参考になりました。
おばあちゃんの話
①行方不明登山者が出ると、地元の猟師さんは、自分の仕掛けたワナを見に行く。自分のワナだと気が悪いから。バリエーションルートとかいって獣道のようなところを単独で歩くのは、そういうリスクもあるのかと思いました。
②数年前も、行方不明の方が出て、奥さんはその後、毎日、行方不明者捜索協力のチラシを登山口で配っていた。半年後、地元の猟師さんが、まさかこんなところ、というところでザックを発見した。それで、ようやく葬式が出せると奥さんは感謝されて、地元に御礼の品を配った。
今回も、警察や消防の方は行方不明の方の写真を見せて、「この方を見られませんでしたか」と捜査されています。
今回同行した、私の所属する山岳会の理事長は、ザックに大きく「京都 ○○(苗字)」と書かれています。
今のご時世ですと、「なんでそんな個人情報(苗字だけで、住所とか個人を特定できるものではないですから個人情報でもないですが)を無防備にさらすんですか」
というツッコミがありそうですが、山では、それぞれ自分の存在を他者に知らせることがいざというときの生存につながるからだとお伺いしました。
山で挨拶するのはマナーというより、いざというとき、「あっ、その人とあそこですれ違いました」という情報が命を助けるかもしれない、ということ。
ですから、所属山岳会ではテントには必ず山岳会名を明記しています。
「ああ、あそこであの山岳会のテントがあって、一緒でした」という目撃証言が命を救う、そんな状況を、避けたいのは当然ですが。
今日は、MTBで朝早くから走る予定にしていたのですが、前夜に所属山岳会より、遭難者捜索の要請があり、参加しました。
遭難者は68歳の男性で、4日前に愛宕山に登り、下山していないとのこと。愛宕山というのは、シビアな山ではないのですが。
警察や消防も捜索したけれど、京都府山岳連盟に協力の要請があり、私の所属している山岳会も岳連加盟のため、情報が届いた次第。
登山道他はくまなく捜索したけれど、発見できず、岳連には、沢筋中心に捜索して欲しいとのこと。
所属山岳会からのメールも、沢装備で懸垂下降ができる人、というオーダー。
私も会に入ってからそのへんのことを学ばせていただいたので、参加した次第。
朝、6時半に愛宕山の登山基地である清滝というところが集合場所。家を6時に出てコンビニで行動食等を買い、6時10分発で、遅刻しそうで申し訳ないと思ったけれど、シティコミュータークロスバイク・リアキャリア付き、に登山ザックをくくりつけて、無理なく走ったら、清滝にはパンクチュアルに着き、ウチから清滝は、たった20分か、私が毎日通勤している大阪・梅田から会社までの歩きの時間よりも近い、と右京区民にとって愛宕がいかに近いのか、改めて認識した次第。
で、集合地点には岳連加盟山岳会の方々が集合されており、担当を決めてそれぞれのエリアを捜索。亀岡の山岳会等の方々は、別の地点を出発して捜索。
沢筋中心に捜索したのですが、見つからず、愛宕神社のところでは右京警察の方4名と出会い、状況を報告。
下山も登山道外のところを含めて捜索しました。下山したところで消防の方と出会いました。消防の方は、これまでかなり大規模で捜索されて、滑落しそうなところとか登山道はくまなく捜索したけれども、見つからないとのこと。
通常、警察や消防は、「ここに遭難者がいる」ということが明かな場合、解決に向けた体制を組みますが、登山届けがなく、「どこに登ったのかよくわからないんですけど、帰ってこないんです」という登山行方不明者には、捜索範囲が特定できないため、対応が限られてしまうようです。
警察や消防を大規模に動員するということは、その分、別の場所での対応には負担になるわけで、公共の安寧に携わる立場としては、特定の案件だけに関わるわけにはいかないのは、市民感覚・納税者感覚としても仕方ないところでしょう。
ですから、登山届けというのは重要な意味を持つと、改めて認識しました。登山届け無しで行方不明になった人には、対処方法がどうしても限定されますが、きちんと登山届けがしかるべきところに出されていれば、当局としても、対応の仕方が判りやすい、ということでしょう。
今回の場合の愛宕山というのは京都近辺の人にとって火伏せの神様として親しまれており、山頂付近に愛宕神社があることもあって、愛宕さんに登るのに、いちいち登山届けを出す、という習慣はありません。「登山」ではなく「神社への参拝」なのに登山届けがいるんかい、という人がいるかもしれませんし。
では、なんで、警察や消防がすごい体制で臨んだかというと、遭難者のバイクが登山口にあったため。
それで、遭難者は確実にここから登って、ここに降りようとしていたという推論が成り立ち、警察消防は行動範囲が推測できるため、体制を組んだ、ということらしいです。
でも、これだけ探しても見つからない。神隠しにあったのか、そんな気持ちで解散しました。
その後、地元の人と話す機会があり、おばあちゃんですけど、参考になりました。
おばあちゃんの話
①行方不明登山者が出ると、地元の猟師さんは、自分の仕掛けたワナを見に行く。自分のワナだと気が悪いから。バリエーションルートとかいって獣道のようなところを単独で歩くのは、そういうリスクもあるのかと思いました。
②数年前も、行方不明の方が出て、奥さんはその後、毎日、行方不明者捜索協力のチラシを登山口で配っていた。半年後、地元の猟師さんが、まさかこんなところ、というところでザックを発見した。それで、ようやく葬式が出せると奥さんは感謝されて、地元に御礼の品を配った。
今回も、警察や消防の方は行方不明の方の写真を見せて、「この方を見られませんでしたか」と捜査されています。
今回同行した、私の所属する山岳会の理事長は、ザックに大きく「京都 ○○(苗字)」と書かれています。
今のご時世ですと、「なんでそんな個人情報(苗字だけで、住所とか個人を特定できるものではないですから個人情報でもないですが)を無防備にさらすんですか」
というツッコミがありそうですが、山では、それぞれ自分の存在を他者に知らせることがいざというときの生存につながるからだとお伺いしました。
山で挨拶するのはマナーというより、いざというとき、「あっ、その人とあそこですれ違いました」という情報が命を助けるかもしれない、ということ。
ですから、所属山岳会ではテントには必ず山岳会名を明記しています。
「ああ、あそこであの山岳会のテントがあって、一緒でした」という目撃証言が命を救う、そんな状況を、避けたいのは当然ですが。
最近のコメント